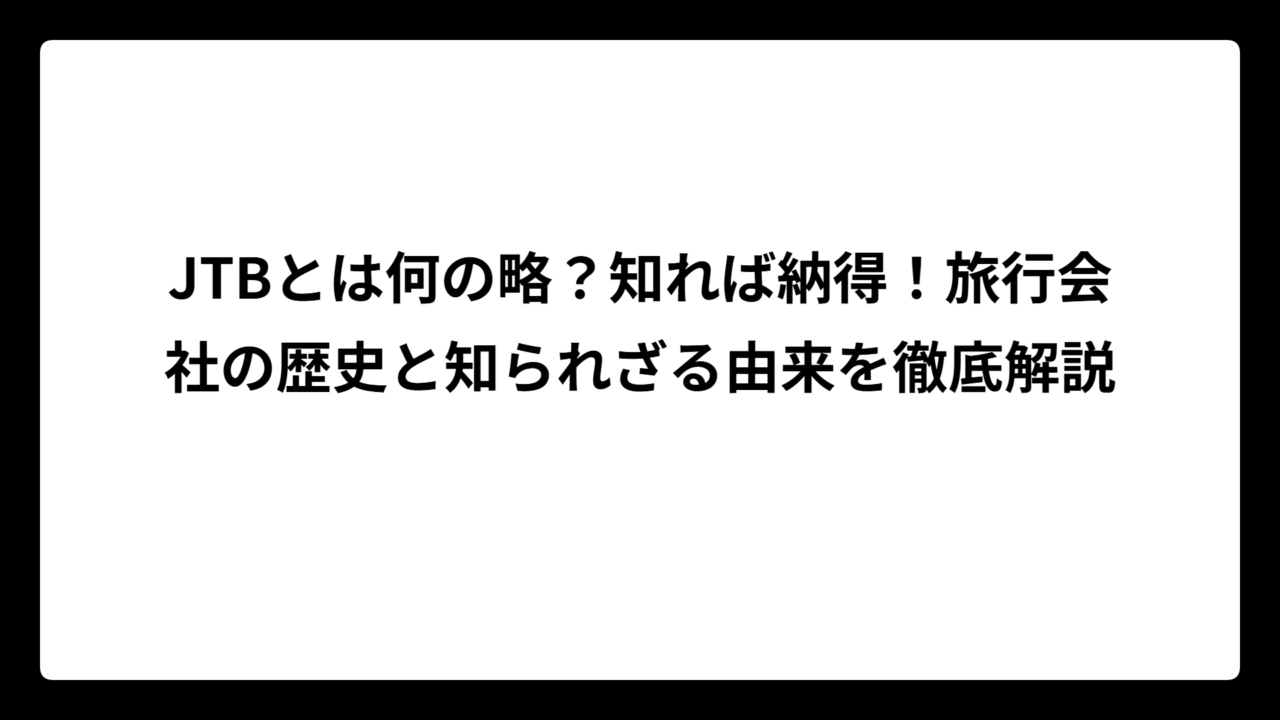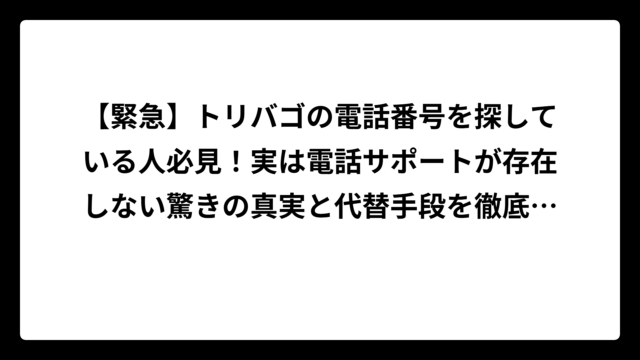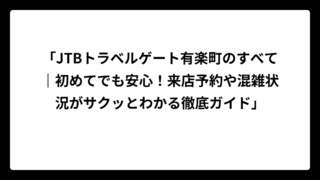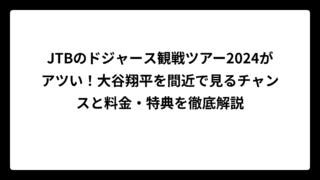旅行会社の大手として知られるJTB。私たちの旅行計画に欠かせない存在ですが、そもそも「JTB」という名称が何の略称なのか知っていますか?実は、この3文字には100年以上の歴史と、日本の観光産業の発展が凝縮されているのです。
今回は「JTBとは何の略か」という素朴な疑問から始まり、創業の歴史、社名の変遷、そして現在のJTBが展開する幅広い事業内容まで詳しく解説します。旅行好きな方はもちろん、企業研究をしている学生さんや、ビジネスパーソンにとっても役立つ情報が満載です。
記事のポイント!
- JTBの正式名称と略称の意味を詳しく解説
- 100年以上にわたるJTBの歴史と社名変遷の全容
- 旅行会社としてだけでなく多角的に展開するJTBの現在の事業内容
- JTBと他の旅行会社との違いや特徴的なサービス
JTBとは何の略なのか?知っておきたい基本情報
- JTBとは「Japan Travel Bureau」の略である
- ジャパン・ツーリスト・ビューローとしての創業の歴史
- 日本交通公社からJTBへの社名変更の経緯
- JTBの設立目的は外国人に日本の真の姿を知ってもらうこと
- JTBグループの現在の企業規模と事業展開
- JTBのロゴマークとブランドイメージの変遷
JTBとは「Japan Travel Bureau」の略である

JTBとは、「Japan Travel Bureau」の頭文字を取った略称です。日本を代表する旅行会社として広く知られていますが、この略称の由来は意外と知られていません。「Japan Travel Bureau」は「日本交通公社」の英語表記であり、長い間公式の英語名称として使用されてきました。
現在は「株式会社JTB」という社名になっていますが、元々は「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」として1912年に創設されました。当時の英語表記は「Japan Tourist Bureau」でした。その後、1945年に「財団法人日本交通公社」と改称された際に英語名が「Japan Travel Bureau」となり、このJTBという略称が定着していきました。
興味深いことに、JTBという略称は長い間正式名称として使われていたわけではなく、親しみやすさから通称として使われていました。しかし、時代とともにこの略称の方が一般に広く認知されるようになり、2001年に商号を「株式会社ジェイティービー」に変更、さらに2018年には「株式会社JTB」として正式に略称を社名に採用するに至りました。
このように、JTBの社名の変遷は、日本の観光産業の発展とともに歩んできた歴史そのものを映し出しています。単なる略称ではなく、日本の旅行文化を支え続けてきた企業のアイデンティティを表す重要なシンボルなのです。
JTBという略称は、現在ではブランド価値を持つ固有名詞として確立しており、日本国内だけでなく世界中の旅行者に認知されています。
ジャパン・ツーリスト・ビューローとしての創業の歴史
1912年3月(明治45年)、当時の鉄道院の木下淑夫が「外客誘致論」を展開したことがJTB創業のきっかけとなりました。木下は、英米人に日本の真の実情(姿)を知ってもらうことを目的としていました。この構想に木下の上司である鉄道院副総裁の平井晴二郎が共鳴し、鉄道院の協力を得て「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」が創立されました。
創業時の面白いエピソードとして、「ビューロー」という言葉が当時の日本人には馴染みがなく、しばしば「ビヤホール」と間違われたということが残っています。しかし、その後急速に事業を拡大し、1913年には神戸、下関、横浜、長崎などに次々と案内所を開設。特に長崎は上海や香港から避暑に来る外国人も多く、長崎案内所からは海外各方面に2,000通もの紹介状を送ったと記録されています。
1913年6月には機関誌「ツーリスト」を発行し、事業の紹介と全国の案内所・支部・本部間の連絡を密にする目的で活用されました。この機関誌は、当時の著名なグラフィックデザイナー杉浦非水氏がデザインした美しい表紙が特徴で、富士山に桜草を配した五色刷りの雑誌でした。
1916年7月には同じく杉浦非水氏のデザインによる「白雪を頂く富士山に帆掛舟のJTB」というデザインの徽章(社章)を制定しました。これがJTBの最初の企業シンボルとなり、同時に企業初の宣伝ポスターも製作されました。
こうして、外国人観光客に日本の魅力を伝えるという明確な使命のもとに創業されたジャパン・ツーリスト・ビューローは、その後日本の観光産業の基礎を築く存在となっていきました。現在の日本が観光立国として世界中から注目される基盤は、この時代に形成されたと言っても過言ではないでしょう。
日本交通公社からJTBへの社名変更の経緯
第二次世界大戦後の1945年9月、戦時中に「財団法人東亜交通公社」と改称されていた組織は、日本の敗戦によりポツダム宣言を受諾したことを機に「財団法人日本交通公社(JAPAN TRAVEL BUREAU)」と改称しました。この改称により、英語表記が「Japan Travel Bureau」となり、これが現在のJTBの直接の由来となっています。
その後、1963年11月12日に財団法人日本交通公社の営業部門を完全に分離し、「株式会社日本交通公社」が設立されました。本社は東京都千代田区丸の内一丁目の交通公社ビル(現在の丸の内オアゾがある場所)に置かれました。この時点でも正式社名は「日本交通公社」でしたが、「JTB」の略称も広く使用されていました。
注目すべきは1988年10月のCIの導入です。この時に「JTB」の浸透に向けてシンボルマークが刷新されました。「JTB」という略称がより広く認知されるようになったきっかけのひとつとして、1979年に放送が始まったTBSの人気番組「クイズ100人に聞きました」での露出が挙げられます。この番組では、優勝者が「ルックJTB」のハワイ旅行を獲得できるという企画があり、司会の関口宏さんから「LOOK JTB」のカバンを渡されるシーンが印象に残ったという人も多いようです。
2001年1月1日には、正式に商号を「株式会社ジェイティービー(JTB Corp.)」に変更し、本社を東京都品川区東品川二丁目(シーフォートスクエア内)に移転しました。さらに2018年1月1日には、商号を「株式会社JTB」に変更しました。これは2002年11月の商業登記法の改正でアルファベットを登記上の商号に使用できるようになったためです。
このように、JTBの社名変更は時代の流れとともに変化してきましたが、「Japan Travel Bureau」の頭文字を取った「JTB」という略称は、一貫して企業のアイデンティティとして継承されてきました。社名が変わっても、JTBという略称が持つブランド価値は不変であり続けています。
JTBの設立目的は外国人に日本の真の姿を知ってもらうこと
JTBの設立には明確な目的がありました。創設者の一人である木下淑夫(当時の鉄道院職員)は、英米人たちに日本の真の実情(姿)を知ってもらうことを目的とした「外客誘致論」を展開しました。これは単なる観光促進ではなく、国際理解を深めるという文化的・外交的な意味合いも持っていました。
当時の日本は明治維新を経て急速に近代化が進む一方で、国際社会における認知度や理解はまだ十分ではありませんでした。日本の美しい自然や伝統文化、産業発展の姿を外国人に直接見てもらうことで、国際的な評価を高めようという戦略的な意図がありました。
この「外客誘致論」に木下の直属上司である鉄道院副総裁の平井晴二郎が共鳴し、鉄道院の協力を得てジャパン・ツーリスト・ビューローが創立されたのです。設立当初から国の機関と密接に連携した組織であったことが特徴です。
設立後は急速に事業を拡大し、全国各地に案内所を設置していきました。1913年から1914年にかけては、神戸、下関、横浜、長崎に案内所を開設し、さらには海外の主要都市にも案内所網を広げました。これらの案内所は、外国人観光客に対する情報提供や旅行手配のサポートを行う拠点として機能しました。
また、1915年1月には東京案内所で外国人に対する鉄道院委託乗車券の販売を開始しました。これは「インフォメーションするだけで切符のお世話をしないのでは、あっ旋の完全を期しがたい」という考えからでした。この販売された乗車券は大型ペーパー式で和英両文で表示され、通用期間は3ヵ月と長く、いつでも途中下車ができるという特典付きという、外国人観光客に配慮した内容でした。
この設立目的と初期の活動は、現在のJTBの企業理念「21世紀のツーリズム発展の一翼を担い、内外にわたる人々の交流を通じて、平和で心豊かな社会の実現に貢献する」にも通じるものがあります。観光を通じた国際交流という創業時の理念は、100年以上経った今でもJTBのDNAとして受け継がれているのです。
JTBグループの現在の企業規模と事業展開

JTBは現在、日本の旅行業界では最大かつ世界有数の事業規模を持つ企業グループとなっています。ユーロモニター社の集計によれば、2013年度のグループ取扱額は、旅行会社として世界第7位、店舗を持つ旅行会社としては世界第3位という規模です。
JTBグループの事業領域は、従来の旅行業の枠を超えて多角的に展開されています。主な事業は以下のように分類されています:
- ツーリズム事業:
- 国内旅行:「エースJTB」などのパッケージツアー
- 海外旅行:「ルックJTB」などのパッケージツアー
- 「旅物語」(メディア型直販商品)
- エリアソリューション事業:
- 地域活性化事業
- ふるさと納税事業(「ふるぽ」など)
- 出版事業(JTB時刻表、旅行雑誌「るるぶ」など)
- ビジネスソリューション事業:
- 法人向け出張管理(BTM事業)
- MICEビジネス(会議・インセンティブ・国際会議・展示会)
- 法人向けITソリューション
- グローバル領域:
- 訪日インバウンド事業
- 海外新興市場(BRICS、ASEAN諸国)での事業展開
社員数も非常に多く、2023年9月末現在の連結従業員数は19,053名に上ります。また、2022年3月期の売上高は連結で5,823億2,300万円となっています。
JTBのグループ会社も非常に多岐にわたります。国内では「JTBガイアレック」「JTBグローバルアシスタンス」「JTBパブリッシング」など様々な専門分野に特化した子会社があり、海外にも多数のグループ企業を保有しています。
近年は新型コロナウイルスの影響で旅行業界全体が大きな打撃を受け、JTBも2020年11月には約6,500人の人員削減を発表し、2021年には資本金を22億4千万円から1億円に減資するなど事業再構築に取り組んでいます。しかし、創業以来築き上げてきたブランド力と顧客基盤を活かし、コロナ後の回復に向けて動き出しています。
このように、JTBは単なる旅行会社を超えて、観光業を中心とした「交流創造事業」を幅広く展開する企業グループへと進化しています。旅行業で培ったノウハウや人脈を活かした新規事業開発にも積極的で、時代のニーズに合わせた事業展開を続けているのです。
JTBのロゴマークとブランドイメージの変遷
JTBのロゴマークとブランドイメージは、100年以上の歴史の中で時代とともに変化してきました。その変遷はJTB自身の発展と日本の観光産業の進化を映し出す興味深いものです。
最初のJTBの企業シンボルは、1916年7月(大正5年)に制定された徽章(社章)です。これは、当時の著名なグラフィックデザイナーであった杉浦非水氏がデザインしたもので、「白雪を頂く富士山に帆掛舟のJTB」というデザインでした。日本を代表する景観である富士山を配し、旅のイメージを帆掛け舟で表現した、日本らしさを強調したデザインでした。
その後、1963年に株式会社日本交通公社として独立する際には、新たな社章が制定されましたが、大きな転機となったのは1988年10月のCI(コーポレート・アイデンティティ)導入です。この時に「JTB」浸透に向けてシンボルマークが刷新されました。新しいJTBマークのデザインとコーポレートカラーである「ダイナミックレッド」は、「若々しく先進的な」JTBの企業イメージを表現するものでした。
この新しいCI導入にあたっては、「かわります。みなさまのJTBでございます。(日本交通公社からJTBへ)」というキャッチコピーで、テレビコマーシャルをはじめ、新聞・雑誌・冠イベント等、新タイライン「For Your Travelife」とともに、大々的なキャンペーンが行われました。
2001年の株式会社ジェイティービーへの商号変更の際も、JTBマークは継承されましたが、新たにブランドスローガン「For Your Travel & Life〜世界をつなぐ旅と心〜」が制定されました。
さらに2006年の新グループ経営体制への移行時には、「常にお客様の立場に立って、最良のサービスを提供し、お客様の夢を実現する。その結果、JTBグループが、お客様にとって無くてはならないパートナーとして認められること」をJTBグループの夢として、新タイライン「Your Global Lifestyle Partner」が制定されました。
そして2011年には、2012年3月の創立100周年を見据え、ブランドメッセージ体系「The JTB Way」が策定され、その中で新たなブランドスローガンとして「感動のそばに、いつも。」(英語表記は「Perfect moments, always」)が定められました。
これらのロゴやスローガンの変遷は、JTBが単なる旅行会社から、お客様のライフスタイル全体をサポートする「交流創造事業」へと事業領域を拡大していく過程を象徴しています。初期の富士山と帆掛け舟という日本的なイメージから、グローバルに通用するシンプルでモダンなロゴへと変化していく中にも、「旅を通じた感動の提供」というJTBの核となる価値観は一貫して表現され続けています。
現在のJTBのロゴマークは、シンプルでありながらも強い印象を与えるデザインとなっており、国内外で高い認知度を誇っています。このロゴマークはJTBのブランド価値を象徴する重要な資産となっているのです。
JTBとは何の略か?知っておくべき企業の実態と特徴
- JTBの企業としての現在の位置づけ
- 日本の旅行会社としてJTBが持つ強みとは
- JTBと他の旅行会社との違い
- JTBが提供する多様なサービスの内容
- ジャパントラベルビューローとしての原点と変革
- JTBのビジネスモデルがどう進化しているのか
- まとめ:JTBとは何の略かだけでなく幅広い事業を展開する企業
JTBの企業としての現在の位置づけ
JTBは現在、日本の旅行業界では最大手であり、世界的にも有数の規模を持つ旅行会社です。しかし、単なる旅行会社というだけではなく、「交流創造事業」を展開する総合サービス企業として位置づけられています。
組織形態としては、株式会社JTBが事業持株会社として、多様な事業を展開するグループ企業を統括しています。2018年4月には、2006年に分社化した地域会社など計20社を本社に統合し、組織の効率化と経営の合理化を図りました。この再統合は「第3の創業」とも称され、オンライン旅行会社(OTA)などの新興勢力に対抗するための戦略的な動きでした。
資本金は2021年3月に22億4千万円から1億円へと減資しましたが、これはコロナ禍における経営効率化の一環と考えられます。株主構成は多様で、公益財団法人日本交通公社をはじめ、JR各社(東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、九州旅客鉄道、北海道旅客鉄道、四国旅客鉄道)、航空会社(日本航空、ANAホールディングス)、銀行(三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行)など、交通・金融を中心とした日本を代表する企業が名を連ねています。
JTBは旅行業登録(観光庁長官登録旅行業第64号)を保持しており、JRの乗車券類委託発売指定を受けています。これは、JTBが日本の公共交通システムと密接に連携していることを示しています。
また、近年ではデジタル化の波に対応するため、インターネット販売にも力を入れています。1998年4月にはインターネット上で旅の予約から決済までを一括して行うシステム「JTB INFO CREW(インフォ クルー)」のサービスを開始し、2000年3月にはヤフー(株)・ソフトバンクグループとインターネットによる旅行販売会社「(株)たびゲーター」を設立しました。
さらに、コロナ禍を経て、JTBは事業構造の見直しを進めています。2020年11月には約6,500人の人員削減を発表し、新卒採用の見送りも決定しました。また、2021年9月には東京都品川区の本社ビルと大阪市中央区のビルを売却しました(本社ビルについては引き続き賃貸契約を結んで利用)。
このように、JTBは日本の旅行業界のリーダーとしての地位を維持しながらも、経営環境の変化に対応して自らを変革し続けています。「Japan Travel Bureau」という略称の由来となった国際的な観光促進という創業時の使命は今も変わりませんが、その実現方法は時代とともに進化を続けているのです。
日本の旅行会社としてJTBが持つ強みとは

JTBが日本の旅行業界でトップの地位を長年維持してきた背景には、いくつかの独自の強みがあります。
まず挙げられるのは、100年以上にわたる歴史の中で築き上げてきた「ブランド力」です。JTBは1912年の創業以来、日本の観光産業の発展とともに歩んできました。その長い歴史の中で培われた信頼感は、他社には簡単に真似できない無形の資産となっています。特に年配の世代を中心に、「旅行=JTB」というイメージが強く定着しており、安心・安全な旅行を求める顧客からの高い支持を得ています。
2つ目の強みは「圧倒的な店舗ネットワーク」です。JTBは全国に数多くの店舗を展開しており、対面での接客サービスを重視するお客様にとって便利な体制を整えています。また、これらの店舗は単なる販売拠点というだけでなく、地域の観光情報の発信拠点としても機能しており、地域と密着した観光振興にも貢献しています。
3つ目は「幅広い商品ラインナップ」です。JTBは海外旅行の「ルックJTB」、国内旅行の「エースJTB」をはじめ、団体向け旅行、法人向け出張管理サービス、訪日外国人向け旅行など、多様なニーズに対応した商品・サービスを提供しています。また、旅行商品だけでなく、時刻表や旅行ガイドブック「るるぶ」の出版など、旅行に関連する幅広い情報提供も行っています。
4つ目は「強力なパートナーシップ」です。JTBは航空会社、鉄道会社、ホテル・旅館、観光地など、多くの事業者と強固な関係を築いています。特にJR各社や日本航空、ANAなどの主要交通機関とは資本関係も含めた緊密な協力体制があり、これが競争力の源泉となっています。
5つ目は「グローバルなネットワーク」です。JTBは世界各国に拠点を持ち、海外の観光情報の収集や現地でのサポート体制を整えています。この国際的なネットワークは、海外旅行商品の企画・販売だけでなく、訪日外国人(インバウンド)向けのサービス提供にも活かされています。
6つ目は「観光に関する豊富な知見とデータ」です。JTBは長年の事業を通じて蓄積した観光に関するノウハウやデータを持っており、これを活かした地域振興や観光政策の提言なども行っています。株式会社JTB総合研究所を通じて、観光に関する調査・研究も積極的に展開しています。
これらの強みを総合的に活かすことで、JTBは変化の激しい旅行市場においても競争力を保ち続けています。特に近年はデジタル化の進展に対応するため、オンラインサービスの強化にも注力していますが、その背景には長年培ってきた実店舗でのサービス品質やブランド力があります。JTBの強みは、単に規模が大きいということだけではなく、歴史の中で築き上げてきた多面的な価値提供能力にあると言えるでしょう。
JTBと他の旅行会社との違い
JTBと他の主要旅行会社との違いを理解することは、旅行会社を選ぶ際の参考になるでしょう。ここでは、JTBと他の旅行会社(HIS、近畿日本ツーリスト、日本旅行など)との主な違いを比較してみます。
まず、設立背景と歴史の違いがあります。JTBが1912年に国策としての「外客誘致」を目的に設立されたのに対し、HISは1980年に創業した比較的若い企業で、当初から民間企業として「格安航空券」をビジネスの中心に据えていました。近畿日本ツーリストは1941年に「新日本交通公社」として設立され、1955年に「近畿日本鉄道観光社」を経て現在の社名になりました。日本旅行は1905年に「大阪鉄道旅行案内所」として設立され、長い歴史を持ちますが、主に西日本を基盤に発展してきた経緯があります。
次に、ビジネスモデルの違いです。JTBは総合旅行会社として幅広いサービスを提供し、店舗ネットワークを重視した事業展開をしていますが、HISは格安航空券の販売を原点に、インターネット販売を積極的に活用し、独自の海外ネットワークを構築しています。近畿日本ツーリストは法人向けビジネス(特にMICE分野)に強みを持ち、日本旅行はJR西日本グループの一員として、鉄道と連携した旅行商品に特色があります。
ブランドイメージにも違いがあります。JTBは「安心・信頼・高品質」というイメージが強く、主に中高年層や家族旅行に支持されています。一方、HISは「若者向け・格安・冒険的」というイメージがあり、主に若年層や個人旅行者に人気です。近畿日本ツーリストは「ビジネス向け・専門性」、日本旅行は「国内旅行・鉄道旅行」というイメージが強いでしょう。
以下の表は、主要旅行会社の特徴を比較したものです:
| 会社名 | 創業 | 主な強み | ターゲット顧客 | ブランドイメージ |
|---|---|---|---|---|
| JTB | 1912年 | 総合力、店舗ネットワーク | 幅広い年齢層、家族 | 安心、信頼、高品質 |
| HIS | 1980年 | 格安航空券、独自海外拠点 | 若年層、個人旅行者 | 若者向け、格安、冒険的 |
| 近畿日本ツーリスト | 1941年 | MICE事業、法人向けサービス | ビジネス客、団体旅行 | ビジネス向け、専門性 |
| 日本旅行 | 1905年 | 鉄道旅行、国内旅行 | 国内旅行者、鉄道ファン | 国内旅行、鉄道旅行 |
もう一つ重要な違いは、商品開発のアプローチです。JTBは「高品質・安心」を重視した商品が特徴で、比較的価格帯も高めです。対してHISは「価格競争力」を重視し、独自の仕入れルートを活かした格安商品を多く提供しています。近畿日本ツーリストはビジネス旅行や団体旅行向けの専門的なプランニング、日本旅行はJRとの連携による鉄道を活かした旅行商品に特色があります。
また、グローバル展開の方向性も異なります。JTBは世界各国に拠点を持ち、訪日外国人向けのサービスにも力を入れています。HISも海外に多くの拠点を持ちますが、ホテル事業など観光以外の事業多角化も積極的に進めています。近畿日本ツーリストと日本旅行は海外展開もしていますが、規模としてはJTBやHISほど大きくありません。
これらの違いを理解した上で、自分の旅行スタイルや予算、重視するポイントに合わせて旅行会社を選ぶことが大切です。JTBは安心・信頼を重視する方や、きめ細かいサービスを求める方に適している一方、価格重視の若い世代にはHISなど他社の方が合っている場合もあるでしょう。
JTBが提供する多様なサービスの内容

JTBは旅行会社としてだけでなく、多様なサービスを提供する総合的な「交流創造事業」を展開しています。その幅広いサービス内容を見ていきましょう。
1. 旅行関連サービス JTBの中核事業である旅行サービスには、以下のようなものがあります:
- パッケージツアー:「ルックJTB」(海外旅行)や「エースJTB」(国内旅行)などのブランドで、交通機関とホテルがセットになった旅行商品を提供しています。
- 個人旅行向けサービス:航空券やホテルの手配、レンタカー予約など、旅行の各要素を個別に提供するサービスです。
- 団体旅行サービス:学校の修学旅行や企業の招待旅行など、団体向けの旅行プランを企画・実施します。
- 法人向け出張管理(BTM)サービス:ビジネストラベルの予約・管理・精算を一元化するサービスで、企業の出張コスト削減に貢献します。
- MICE(会議・インセンティブ・国際会議・展示会)サービス:企業や団体向けに、大規模イベントや国際会議の企画・運営をサポートします。
2. 情報提供サービス 旅行に関連する様々な情報を提供するサービスも展開しています:
- 出版事業:「JTB時刻表」や旅行ガイドブック「るるぶ」を発行しています。「るるぶ」はギネス世界記録™に「発行点数世界最多の旅行ガイドシリーズ」として認定されています。
- 観光情報サイト:インターネット上で旅行情報を提供するウェブサイトを運営しています。
3. 地域活性化サービス JTBは地域振興や観光開発にも力を入れています:
- DMO(観光地域づくり法人)支援:地域の観光資源を活かした持続可能な観光地域づくりをサポートします。
- ふるさと納税支援:ポータルサイト「ふるぽ」を通じて、自治体のふるさと納税制度を支援しています。旅行クーポンを返礼品に加えることで、実際に地域を訪れるきっかけを作っています。
- 地域イベント企画・運営:地域の祭りや伝統行事の企画・運営をサポートし、観光客誘致に貢献しています。
4. 訪日外国人向けサービス 増加する訪日外国人に向けたサービスも充実しています:
- 訪日ツアー:「サンライズツアー」ブランドで外国人向けの日本国内観光ツアーを企画・催行しています。
- 多言語観光案内:外国人観光客向けの多言語対応観光案内所を運営しています。
5. その他の事業 さらに幅広い事業を展開しています:
- ギフト商品:「JTBナイスギフト」などの商品券を発行しています。
- 保険サービス:ジェイアイ傷害火災保険と提携し、旅行保険をはじめとする各種保険を提供しています。
- 人材サービス:旅行業界に関連する人材育成・教育事業を行っています。
このように、JTBは単なる旅行の手配だけでなく、観光に関連する様々なサービスを総合的に提供しています。これは、1912年の創業以来、日本の観光産業の発展とともに事業領域を拡大してきた結果と言えるでしょう。「Japan Travel Bureau」という名称の由来となった外国人観光客の日本への誘致という創業時の使命は、現在も様々な形で継承されているのです。
ジャパントラベルビューローとしての原点と変革
JTBの歴史は、1912年(明治45年)3月に設立された「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」にさかのぼります。この名称が現在のJTB(Japan Travel Bureau)の原点となっています。創業時の目的や事業内容から、現在に至るまでの変革を見ていきましょう。
創業時のジャパン・ツーリスト・ビューローは、外国人に日本の真の姿を知ってもらうことを目的としていました。当時の鉄道院の木下淑夫が提唱した「外客誘致論」がきっかけとなり、木下の上司である鉄道院副総裁の平井晴二郎の協力を得て設立されました。設立当初は会長に平井晴二郎、理事の一人として木下淑夫が名を連ねています。
創業後、ジャパン・ツーリスト・ビューローは急速に事業を拡大していきました。1913年には神戸、下関、横浜、長崎に次々と案内所を開設し、1914年には海外の主要都市にも案内所網を張り巡らせました。また、1915年には東京案内所で外国人向けの鉄道院委託乗車券販売を開始するなど、着実に事業基盤を固めていきました。
第一次世界大戦の影響で外国人観光客数が伸び悩む中、1925年には日本人向けの国内旅行事業にも進出し、邦人客向けの内地各地行き鉄道切符の販売を開始しました。これは自主財源確保の一環でしたが、当時の日本人の旅行熱の高まりもあり、成功を収めました。
1927年には社団法人ジャパン・ツーリスト・ビューローとなり、事業の拡大に対応した組織改革を行いました。その後、1934年には社団法人ジャパン・ツーリスト・ビューロー(日本旅行協会)と改称し、邦人部門を強化するため国内旅行の利用者団体である既存の「日本旅行協会」の事業を吸収しました。
第二次世界大戦中は「東亜旅行社」、「東亜交通公社」と社名を変更しましたが、戦後の1945年9月に「財団法人日本交通公社(JAPAN TRAVEL BUREAU)」と改称し、新たなスタートを切りました。この時に英文名称が「JAPAN TRAVEL BUREAU」となり、現在のJTBの直接の由来となっています。
戦後の高度経済成長期には、日本人の旅行需要の増加に伴い事業を拡大。1963年11月には財団法人日本交通公社の営業部門を分離し、「株式会社日本交通公社」として民営化されました。これがJTBの企業としての実質的な出発点です。
その後、1988年にはCI(コーポレートアイデンティティ)を導入し、「JTB」のブランド浸透を図りました。2001年には商号を「株式会社ジェイティービー」に変更し、2018年には「株式会社JTB」とさらに社名を変更しています。
このように、JTBはその長い歴史の中で、時代の変化に応じて組織形態や事業内容を変革させてきました。外国人観光客向けのサービスからスタートし、日本人の国内・海外旅行需要に応え、さらには現代では旅行業にとどまらない「交流創造事業」へと事業領域を拡大しています。
しかし、こうした変革の中でも、「旅を通じた人々の交流促進」という創業時の理念は一貫して引き継がれています。ジャパン・ツーリスト・ビューロー設立時の「外客誘致」の精神は、現在のインバウンド事業や国際交流事業にも生かされているのです。
JTBのビジネスモデルがどう進化しているのか
JTBのビジネスモデルは、創業以来の100年以上の歴史の中で、時代の変化に合わせて大きく進化してきました。特に近年のデジタル技術の発展や消費者行動の変化に対応するため、従来の旅行代理店モデルから脱却し、新たなビジネスモデルへの転換を図っています。
1. 旅行代理店モデルからの進化
JTBの創業期から長らく続いたビジネスモデルは、「チケット・エージェント」としての役割でした。航空券や鉄道券、宿泊施設の予約を代行し、その手数料を収益源とするモデルです。1962年頃からは「セット旅行」(後のパッケージツアー)の販売を開始し、「トラベル・エージェント」へと進化。自社で企画した旅行商品を販売し、交通機関や宿泊施設との価格差を収益とするモデルへと転換しました。
1968年には海外主催旅行「ルック」を発売開始し、1971年には国内主催旅行「エース」も登場。これらのパッケージツアーは長く JTBの主力商品となりました。実店舗を通じた対面販売が中心で、旅行相談やアフターフォローなどのサービス品質が差別化要因でした。
2. インターネット時代への対応
1990年代後半からのインターネットの普及により、旅行業界も大きな変革を迎えます。JTBも1998年4月にインターネットによる旅行販売を開始し、2000年3月にはヤフー・ソフトバンクグループと共同で「たびゲーター」を設立しました。
しかし、この時期にはまだインターネット販売は補完的な位置づけで、主力は依然として店舗販売でした。一方で、Expediaや楽天トラベルなどのOTA(Online Travel Agent)が台頭し始め、特に個人旅行や単品販売(航空券のみ、ホテルのみなど)の分野で市場シェアを拡大していきました。
3. マルチチャネル戦略と事業領域の拡大
2000年代に入り、JTBはインターネット販売の強化と並行して、実店舗・コールセンター・インターネットを組み合わせたマルチチャネル戦略を展開します。2006年には新グループ経営体制に移行し、マーケット(お客様)に正対した会社群によるグループ経営を開始しました。
同時に、単なる旅行販売にとどまらない事業領域の拡大も進めました。MICE(会議・インセンティブ・国際会議・展示会)ビジネスや法人向け出張管理サービス(BTM事業)、地域活性化事業などへの展開です。これらは従来の個人向け旅行販売よりも安定した収益が見込めるビジネスでした。
4. デジタルトランスフォーメーションと新たな収益モデル
近年のJTBは、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、データ駆動型のビジネスモデルへの転換を図っています。単なる旅行商品の販売だけでなく、顧客の行動データや嗜好を分析し、パーソナライズされた旅行提案や、旅行前後を含めた総合的な「体験価値」の提供に力を入れています。
具体的な取り組みとしては以下のようなものがあります:
- ふるさと納税ポータルサイト「ふるぽ」(2014年開設):旅行会社のノウハウを活かした地域支援の新しいモデル
- 企業版ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとコネクト」(2020年開設):地方創生に取り組む自治体と企業のマッチング
- 法人向けソリューション事業:単なる出張手配ではなく、企業の出張戦略全体をコンサルティングするサービス
- 地域活性化事業:DMO(観光地域づくり法人)支援や観光コンサルティングなど
5. コロナ後の新たな戦略
2020年からの新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、旅行業界に壊滅的な打撃を与えました。JTBも2020年11月に約6,500人の人員削減を発表するなど、事業再構築を迫られています。
コロナ後の新たな戦略としては、以下のような方向性が見られます:
- デジタル化のさらなる加速:オンライン販売の強化と実店舗の効率化
- サステナブルツーリズムへの注力:環境負荷の少ない持続可能な観光の推進
- ワーケーションなど新しい旅のスタイルへの対応:生活と仕事と旅行の境界が曖昧になる新しいライフスタイルへの提案
- 地域活性化事業の強化:国内観光の質的向上と地域経済への貢献
このように、JTBのビジネスモデルは、単なる旅行商品の販売から、「交流創造」を軸とした多様なサービス提供へと進化しています。創業時の「Japan Tourist Bureau」としての役割から大きく拡大し、デジタル時代における新たな価値創造に挑戦し続けているのです。
まとめ:JTBとは何の略かだけでなく幅広い事業を展開する企業
最後に記事のポイントをまとめます。
- JTBとは「Japan Travel Bureau」の略で、日本交通公社の英語表記に由来する
- 1912年に「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」として創業し、外国人に日本の真の姿を知ってもらう目的があった
- 1945年に「財団法人日本交通公社」と改称し、この時に英文名称が「Japan Travel Bureau」となった
- 1963年に営業部門が「株式会社日本交通公社」として民営化され、2001年に「株式会社ジェイティービー」、2018年に「株式会社JTB」へと社名変更した
- JTBは日本の旅行業界最大手であり、世界有数の規模を持つ旅行会社である
- 海外旅行「ルックJTB」、国内旅行「エースJTB」などのパッケージツアーが代表的商品
- 出版事業も展開しており、「JTB時刻表」や旅行ガイドブック「るるぶ」が有名
- 近年は旅行業だけでなく、地域活性化事業やふるさと納税事業、法人向けソリューション事業など多角的に事業を展開
- JTBの強みは長年築き上げたブランド力、全国の店舗ネットワーク、幅広い商品ラインナップにある
- 他の旅行会社と比較して「安心・信頼・高品質」というイメージが強く、中高年層や家族旅行に支持される傾向がある
- デジタル時代に対応するため、マルチチャネル戦略やデジタルトランスフォーメーションを推進している
- コロナ禍を経て事業再構築を進めているが、「旅を通じた人々の交流促進」という創業理念は一貫して継承されている
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- https://www.jtbcorp.jp/jp/ourstory/110th/
- https://otonasalone.jp/190733/
- https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12287872
- https://dictionary.goo.ne.jp/word/jtb/
- https://www.tourism.jp/tourism-database/glossary/dmo/
- https://ja.wikipedia.org/wiki/JTB
- https://www.tourism.jp/tourism-database/glossary/ota/
- https://faq.jtb.co.jp/faqs/f6488/
- https://www.jtb-cwt.com/company/outline.html
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。